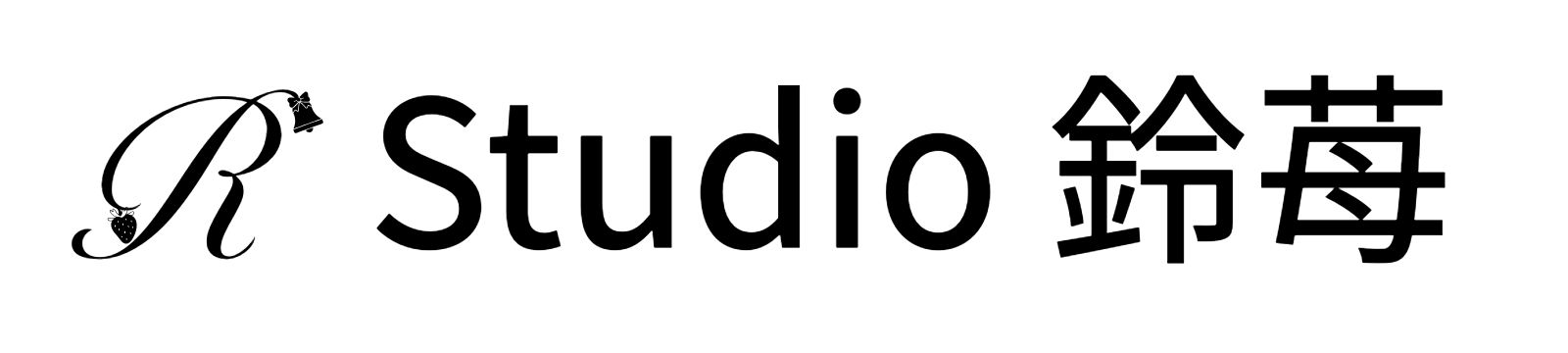読みやすさを左右する文字の大きさ|Web制作で押さえる基本ルール

ホームページを作るとき、文字の大きさを「なんとなく」で決めていませんか?
実はフォントサイズは単なる見た目ではなく、情報の優先順位を伝える大切な設計の一部なんです。
見出し・本文・補足が整理されていないと、ユーザーはどこに注目すればいいのか迷ってしまいますよね。
この記事では、Web制作における文字の大きさの基本ルールを押さえ、誰でも「読みやすい設計のホームページ」を作れるようになるポイントを解説します。
文字サイズは情報設計の出発点
フォントサイズで情報の優先順位を示す
Web制作において、文字の大きさは視覚的な強弱をつけるための基本要素です。
見出しを大きく、本文を標準サイズにし、補足情報を小さくすることで、読む人は自然と情報の流れを理解できます。
もし見出しと本文の差が小さいと、重要なポイントが埋もれてしまい、全体がフラットに見えてしまいます。
逆に見出しを20px以上に設定すれば、ユーザーは「ここが区切りだ」と直感的に気づきやすくなります。
「なんとなく」で決めると読みにくさにつながる
デザインを始めたばかりの方がやりがちな失敗は、フォントサイズを感覚だけで決めてしまうことです。
その結果、本文と見出しがほぼ同じ大きさになり、どこが重要なのか伝わらなくなります。
文字の大きさは、サイト全体の設計と関係しているので「情報の整理」とセットで考えることが欠かせません。
見出し・本文・補足のバランスを考える
見出しは本文よりはっきり大きく
たとえば本文を14pxに設定した場合、見出しは最低でも18px以上にすると差が出ます。
20px以上にするとさらに強調感が増し、読み手にとって直感的にわかりやすい構造になります。
補足情報や注釈は12px程度に抑えると、主役である本文を邪魔せず役割が明確になります。
小さすぎる文字はユーザーの離脱につながる
多くの初心者が避けたいポイントは「本文が小さすぎる」ことです。
14pxを下回ると、とくにスマホでは読みにくくなり、ユーザーはページを離れてしまうリスクが高まります。
Web制作では「小さすぎない」ことも大切なルールです。
数値で覚えると効率的
基準サイズを決めて比率で調整
効率よく設計するなら、本文サイズを基準にして比率で決めるのがおすすめです。
たとえば本文を16pxにすると、見出しは1.25〜1.5倍、補足は0.8〜0.9倍に設定するとバランスが取りやすくなりますよ。
この比率を使えば、サイト全体で統一感を出せます。
デザインツールで見やすさを検証
実際の制作では、ブラウザやデザインツール上で文字の見え方を確認することが重要です。
同じ16pxでもフォントの種類によっては小さく感じたり大きく感じたりします。
最終的には実際の表示で検証することで、理想に近い読みやすさを実現できるので実機検証は大切です。
読みやすさはSEOやUXにも直結する
読みやすい文字は滞在時間を伸ばす
文字の大きさを工夫することはSEOにもつながります。
というのも読みやすいページはユーザーの滞在時間を伸ばし、結果的に検索エンジンからも評価されやすくなるから。
逆に読みにくければ途中で離脱されてしまい、SEO面でも不利になってしまいます。
ユーザーの行動を自然に導く
見出しがはっきりしていると、ユーザーは欲しい情報に素早くたどり着けます。
「探しやすいサイト」として評価が上がり、信頼性にもつながるんです。
Web制作における文字の大きさは、単なる装飾ではなく「行動をデザインする」役割を持っています。
成長のステップとして意識すべきこと
文字サイズ設計を習慣にする
成長のステップとして大切なのは「文字の大きさを常に意識する習慣」を持つこと。
ページを作るときに毎回サイズを考え直すのではなく、最初にルールを決めておくと迷わず効率的に進められます。
読みやすい設計ができると信頼につながる
最終的に「読みやすい設計のホームページ」を作れるようになると、ユーザーからの信頼もグッと高まります。
小さな工夫が積み重なって、プロらしい仕上がりに近づいていきますよ。
次の案件やリピートにつながる力になります。
まとめ
文字の大きさは、Web制作において情報を整理し読みやすくするための大切な設計ルールです。
「なんとなく」で決めるのではなく、見出し・本文・補足の役割を意識して設計することで、サイト全体のクオリティが格段に上がります。
今日から文字サイズに気を配り、「読みやすいホームページ」を実現してみてください。
こうした学びを日々Xでも発信しています。よければのぞいてみてください。